高齢化により増大する医療費をどう抑制するかが、大きな社会問題となっています。終末期における医療費も、その抑制の対象として検討されています。
北陸地方のある県で、65歳以上の約66万人のデータを用いて、死亡1年前からの医療費を調査した報告があります。それによると、1人当たり1年間で約290万円の医療費がかかっており、月別の金額は死亡半年前から顕著に増加し、死亡1カ月前に最大になるそうです。
厚生労働省は、死亡前の1年間にかかる医療費を減らすためにどうすればいいかを考えてきました。そこで注目されたのが、次に紹介するデータです。
死亡前1年間にかかる1人当たりの医療費・介護費を死亡場所別に調べたところ、自宅で死亡する場合は病院や施設で死亡する場合の約3分のlの費用しかかからないというのです。病院や診療所で死亡する人が減り、在宅死の割合が増加すれば、医療費の削減につながることから、国は自宅で最期を迎える「在宅死」をすすめています。
在宅死のためには包括的な地域医療計画が必要
しかし、果たしてそうでしょうか。在宅死の全国平均は13.0%ですが、和歌山県の16.8%から北海道の8.8%まで、都道府県別に大きな差があります。そのため都道府県別に医療費と在宅死の割合を調べたところ、在宅死が増加しても必ずしも医療費は削減されないことがわかっています。
高齢者の終末期では、本人の人生観や価値観を優先した治療やケアが行われなくてはなりません。しかし、これには家族の理解が伴わなければなりません。もし、自宅で患者の容態が変化したら、家族は不安になります。日頃から気軽に相談できる医療スタッフや、24時間診察してくれるような在宅医療のバックアップが必要です。
このような体制が日本全国で整っているのでしょうか。現状は決して十分ではありません。在宅医療は主治医1人が行えるものではありません。24時間対応もあり、多科にわたる医学的問題が発生します。複数の医師や看護・介護スタッフによって患者が支えられ、地域の病院がそれをサポートする体制が必要なのです。
自宅で最期を迎えるためのさまざまな課題
自宅で最期を迎える背景には、多くの社会的問題が付随しています。
たとえば、終末期に、ある人が自宅で息を引き取ったとしましょう。担当していた医師は、診断されていた病気で、予期された結末を迎えたことを承知して、死亡の確認と死亡診断書の発行をする必要があります。
しかし、その時に、主治医の都合がつかず、救急車で病院へ運ばれたとしたらどうなるのでしょうか。初めて診察する患者が死亡して搬送されてきたわけですから、担当の医師は変死(異常死)として所轄警察署に届け出ることも予想されます。
また昨今では、介護を苦に身内を殺害するという事件が散見されます。この場合は、家族が事件を隠匿して病死を装うことがあります。当然、死亡確認の際に、医師は不可解さに気づくべきでしょうし、通報を受けた場合は、警察官は決して見逃してはなりません。
このように、終末期の人が自宅で最期を迎えることでも、背景には変死の取扱いにまつわる諸問題が関係しているのです。
安心して、誰にも気を使うことなく、自宅で最期を迎えられることは重要です。しかし、誤解してはならないことは、病院での医療か、在宅での医療かのどちらか一方を選ぶという問題ではないのです。多くの人が安心して畳の上で最期を迎えられるためには、まだまだ多くの問題が解決されなければなりません。
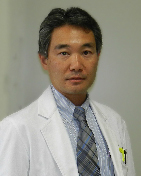
一杉正仁(ひとすぎ・まさひと)
滋賀医科大学社会医学講座(法医学)教授。厚生労働省死体解剖資格認定医、日本法医学会法医認定医、専門は外因死の予防医学、交通外傷分析、血栓症突然死の病態解析。東京慈恵会医科大学卒業後、内科医として研修。東京慈恵会医科大学大学院医学研究科博士課程(社会医学系法医学)を修了。獨協医科大学法医学講座准教授などを経て現職。1999~2014年、警視庁嘱託警察医、栃木県警察本部嘱託警察医として、数多くの司法解剖や死因究明に携わる。日本交通科学学会(理事)、日本法医学会、日本犯罪学会(ともに評議員)など。















