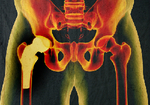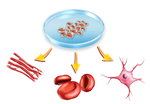患者の欲望から最も遠いiPS細胞の再生医療
再生医療で用いる細胞としては、iPS細胞(人工多能性幹細胞)やES細胞(胚性幹細胞)、体性幹細胞などがある。
「再生医療の中心がiPS細胞であるかのようなイメージが強いですが、細胞治療の供給源としてよりは、疾患の機序や治療法選択への利用、幹細胞研究への貢献など基礎研究的な側面が強い。現時点で患者さんに届いているiPS細胞を用いた治療はひとつもありません」(石塚氏)
それにもかかわらずiPS細胞に大きな予算が配分され、メディアもそればかり取り上げる。日本発の技術とはいえ、あまりにも偏った再生医療全体の全体像となっているのではないかという。
例えば体性幹細胞のひとつである間葉系幹細胞は、軟骨、骨、脂肪、神経や肝細胞、その他組織の細胞へも分化することが報告されている。障害部位に集積する性質を持っており、障害場所で各種サイトカインなどを放出し、細胞を修復するとされている。こちらのほうがより患者さんが求める治療ができるともいえる。
国としてiPS細再生医療は推進したいが それ以外はさほど積極的ではなく、むしろ抑制しているとさえ感じられる傾向があるのも事実だ。
人間の臓器の再生はどこまで可能なのか
ところで細胞培養の技術はどこまで進んできているのか? さほど遠くない未来に臓器そのものを再生できるかのような報道が少なくないがどうかと問うと、石塚氏は笑いながら「臓器の再現などまだまだ無理、人体の機序でわからないことがあまりにも多過ぎます。欠損した一部を補うなら可能性はありますが、臓器そのものを最初から作るなどまだまだ無理です」と言う。
研究や創薬向けの細胞でも機能性の再現が大きな課題だ。仮に多少立体的な構造になったとしても、目的の臓器と同じような機能を持つことが極めて難しいとされる。例えば肝臓に似た細胞の塊ができたとしても、薬剤を代謝する機能を年単位で維持するまでには至らないのだ。現状、血管や神経系の関与が薄い筋芽細胞シートや口腔粘膜細胞シートなどのシート化技術などに注目が集まっている段階だ。
さらに、培養には、研究者の経験に基づく感覚的な技術を含む独自の手法が無数に存在する。自動培養システムなどの話題もあるが、汎用性のあるシステムの確立までにはあまりにも遠い道のりだ。
そもそも、再生医療では、角膜上皮や口腔粘膜など、少量かつ小型な自家移植組織、心筋組織や皮膚組織などの複雑な構造を持つ自家移植組織、さらには大量生産が可能なとなる他家移植組織など、組織によって培養の方法があまりにも多種多様となっている。
一部では、AIを活用した培養システムの構築などといわれるが、石塚氏は「AIは人間が膨大なデータを入力しない限り動かない。その前提となる条件が整ったしっかりとしたデータの集積が存在しないのです。どうやってAIが動くのですか?」と疑問を呈する。