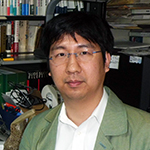この2つの事件から思い出させられるのが、「座敷牢」という死語になったはずの言葉だ。明治から戦前にかけて、精神疾患の患者が閉じ込められた監護部屋は、このように呼ばれた。
日本の精神疾患患者が受けててきた不幸
1900年には「精神病者監護法」という法律が制定されている(1950年廃止)。これは精神病患者の親族に患者の監護を義務づけたもので、いわば「座敷牢」の設置を国家が公認したものだった。
日本における精神医学の創始者とされる呉秀三(1865〜1932年)は、全国の座敷牢を実地に調査し、その調査結果を1918年に『精神病者私宅監置ノ実況及ビ其統計的観察』という本に著した。
狭い土蔵や檻の中に監禁され、外に出ることのかなわない精神病患者の悲惨な状況に、呉秀三はこんな言葉を残した。
「我が邦(くに)十何万の精神病者は実にこの病を受けたるの不幸のほかに、この邦に生まれたるの不幸を重ぬるものというべし」
精神疾患になったことが悲惨なだけでなく、精神疾患の患者が非人間的な処遇を受ける国に生まれたことが、さらに不幸なのだ──。
なぜ親たちは適切な医療を受けさせず「監禁」に?
100年前に精神医学者が残したこの言葉は、今の日本には当てはまらないと言い切ることができるだろうか?
精神疾患は、入院や通院といった適切な医療と服薬をすれば、症状を安定させることのできるケースも多い病だ。それなのに、適切な医療を受けさせず、「監禁」というあってはならない手段に及んだ理由は何だったのか?
日本にいまだ残る精神病患者への偏見が、地域社会の目から患者を隠してしまう方向に、その親たちを及ばせたのかもしれない──。
このような悲劇が起こらないためには、地域においてどのような医療や福祉の体制が必要だったのだろうか。2つの事件が日本の精神保健に突きつけた課題は極めて重い。
(文=里中高志)