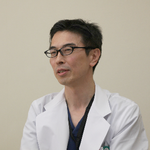最後の10年をどう生きるべきか?shutterstock.com
超高齢社会を迎え、「人生ラスト10年問題」がクローズアップされている。人生の最後に介護を受けたり、医療機関に入ったりする期間が平均で10年にも及ぶのである。この期間を短くするには、どうしたらいいのか? この問題に正面から取り組む、一般社団法人チーム医療フォーラム代表理事の秋山和宏医師に話を聞く。
「今の医療は、ある面において『進歩の罠』におちいっているといえるでしょう」
秋山医師は、「罠」について、マンモス狩を例に説明する。
「原始時代、私たちの祖先はマンモス狩を行っていました。巨大なマンモスを一人で倒すのは無理です。チームを組むようになって、やっと倒せるようになりました。さらに狩の方法を工夫し、一度に三頭、四頭とだんだん多くを倒せるようになりました。ついには、マンモスの群れを崖から追い落とし、群れごと一網打尽できるようになりました。しかし、この"進歩"によってマンモスは激減してしまい、祖先たちは貴重な食料を失ってしまったのです」
医療も同じように、この100年の間、「いかに延命するか」を命題に進歩を続けてきた。その結果、特に先進諸国では人類の寿命はおおいに延び、日本では、男性が平均80.21歳、女性が平均86.21歳(2014年厚労省発表)まで生きられるようになった。
日本人の平均寿命は、戦前で男女とも40歳代、戦争が終わった後の昭和22(1947)年でも、男性50.06歳、女性53.96歳だった。乳幼児の死亡率が高かったことを考えると、大人だけの年齢を平均すればもう少し長生きになるかもしれないが、それでも、還暦を迎えることができれば長寿であると喜ばれたのである。このような状況の中で、人々は「少しでも長く生きたい」と願い、医療関係者や病人の家族も「少しでも長く生かしたい」という価値観で一致していた。
寿命がのびたら、病む期間ものびてしまった
「ところが2000年に、WHO(世界保健機関)が、『健康寿命』という概念を発表しました。これは、平均余命(寿命)から寝たきりなど自立した生活ができない期間を差し引いたものです。つまり、80歳まで生きたとして、自宅で介護を3年受け、入院を3年したとしたら、健康寿命は6年を引いて74歳になります」
と、秋山医師は、世界的な価値観の変化を説明する。
20世紀までは、とりあえず寿命が長くなればよかったのが、それだけでは対応できない状況になってきたため、健康寿命という新しい概念がでてきたのだ。
「厚労省の2010年の発表によると、平均余命と健康寿命の差は、男性がおよそ9年、女性がおよそ12年となります」
つまり、その間は、介護を受けたり医療施設に入ったりして、自立した生活ができない期間ということになる。
「平均余命が50歳ぐらいのころには、寿命と健康寿命は、ほぼ一致していました。寿命が延びたことで、人生最後に約10年もの長い期間、医療や介護が必要となり、本人や家族にとって重い負担となっています」
この10年は「人生ラスト10年問題」と呼ばれている。ピンピンと元気で病むことなくコロリと往生するという意味の「ピンピンコロリ」は、21世紀の高齢者のひとつの理想の姿とされるが、これがなかなか難しいのである。